| 久しぶりにバストゥークを訪れた私が、昔なじみと飲み明かしたのは、大きな月が東の空に浮かんだ晩のことだった。 どれくらいの時が経ったのかあやふやになってきた頃、友に再会を誓いながら気だるさに満ちた腕で酒場の重い扉を開けた。空は既に白んでいた。 ひと晩中薄暗いカウンターで過ごした眼には、少しばかり眩しかった。清々しい風に誘われるままに店先の階段を下りて行くと、そこにはバストゥーク港が広がっていた。 |
 |
|
迷い込んだ路地に重い荷物を置いて、その傍らに腰を下ろしたその時、何かが遮ったような気がして、私は思わず顔を上げた。明け方の空を背に、ひとりの少女が立っていた。酔いが醒めていなかったせいなのだろうか。薄明かりの中に見たその姿は、神々しくさえ感じられた。 少女は微笑んだ。
|
 |
石造りの白い街並みと、わずかに愁いの色を含んだような空が、鮮やかな対比を生み出していた。遠くグスタベルグの山々は、雄大な連なりを誇っていた。 夕日がすっかり沈んでしまう前に、私はバストゥークの街を後にした。茜色に染まった空が浮き彫りにした少女の横顔こそが、何よりも心に焼きついた記憶となって、今もなお色あせずにいる。 (Kauffmann) |
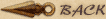 |
