|
|
「ほーら、お姉ちゃんの言ったとおりでしょ!? 冒険なんてまだ早いのよ!」 ふたりのタルタルの少女が、がたがたと震えながらしゃがみ込んでいた。少女たちはどう見ても双子で、おまけに迷子であることも明らかだった。 妹と思われる方は、ただひたすらに泣きじゃくっていた。 |
 |
| 「早くおうちに帰りたいよ〜!」 雷が怖いからなのか、姉に叱られたせいなのか、もはや本人にもわからなくなっている様子だった。 真剣なふたりには大変申し訳ないが、そのかわいらしいやりとりを垣間見て、私は思わず笑ってしまった。 すると、姉の方が駆け寄ってきた。 「ちょっと、旅のお方! 笑ってないで早く助けてください!」 そう叫んだかと思うと、そのまま勢い余って私の膝に鼻をぶつけた。 「ああ、ごめんよ。最初からそのつもりだから安心して」 妹の泣き声は、嘘のようにぴたりと止まった。 私たちは風車の下に身を潜め、危険の多い夜が明けるのを待った。少女たちは随分と腹を空かせていたようで、私が与えた黒パンとソーセージを、瞬く間にたいらげてしまった。満腹になると、ふたりは寄り添って、ほとんど同時に寝息を立て始めた。 翌朝の空は、どこまでも青く深く澄み切っていた。双子も、前日のことをすべて忘れたような顔をしていた。 砂塵混じりの風が吹き出さないうちに、ふたりを連れて発つことにした。 |
 |
それにしても少女たちは実によく跳ね回り、私は幼い子を連れて歩くことが、どんなに大変かを思い知った。 ひとまずは、大きな街まで安全に送り届けてやろうと考えながら、ふたりの後を追って、私も緑の斜面を駆け下りた。 それは、こんないい大人にとっても、たいそう楽しい瞬間だった。 |
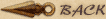 |
