|
|
その晩のことだった。宿屋の片隅で久々の酒を味わっていると、杯を手にしたエルヴァーンの戦士が、私の隣に腰掛けてきた。 「ちょっと失礼。あなた、かなり腕が立ちそうね。明日、時間ある?」 「時間か……呆れるくらいあるな」 「話が早い。その時間、買った」 |
 |
| 翌朝のバルクルム砂丘は、容赦なく降り注ぐ強い陽光を跳ね返し、まるで白銀の世界にも見えた。 女は海岸で探し物を始めた。私はその姿を常に視界に捕らえながら釣りをして過ごし、たまに厄介者を追い払ったりした。つまりは用心棒だ。私を信用したのか、女は鎧を脱ぎ捨てて作業に没頭するようになった。 女が必死で探していたのは、祖父から譲り受けたという剣だった。斬りかかった敵に弾かれ、そのまま夜の波にさらわれてしまったらしい。 誇り高きエルヴァーンの戦士が丸腰では示しがつかない。同じ冒険者には頼みたくなくて、私のような旅人に声を掛けてきたのだろう。 日が傾く頃には、釣り餌も尽きた。波打ち際には、ひとり肩を落としている女の影があった。自力で剣を見つけたいだろうと思い、私はただ傍らで見守っていたが、そろそろ協力を申し出てもいい頃合いだった。 女の方に歩き出したその時だ。何かが日の光を映して鋭く光った。波が引くと、砂に埋もれかかった剣が姿を現した。私は思わず声を上げた。 女は砂を蹴って立ち上がると、潮風に逆らって駆け寄ってきた。 西の空に向かってかざされた剣は、バルクルムの夕日の光に刃を縁取られて、高貴な輝きを帯びた。 |
 |
それを見た女は、ほんの一瞬だけ安堵の表情をのぞかせたが、すぐさま戦士らしい顔つきを取り戻した。 まるで生気を吹き込まれたかのような横顔は、右手の剣にも似た凛とした美しさをたたえていた。その剣は、戦いに生きる者の証であり、女の魂そのものだったのかもしれない。 |
| 砂の町に、再び夜の帳がおりた。その日私は、何故だか酒を飲む気にもなれず、早々に寝てしまった。そして浅い眠りをさまよううちに、昔の夢を見た。 舞台は町の武器屋で、父に初めて剣を買ってもらった日のことだ。それはほんの安物だったが、兄と同じ剣だった。嬉しかった。使えもしない剣を1本携えて歩くだけで、自信と勇気が胸いっぱいにあふれてきた。 まるで英雄の仲間入りをした気分のまま、夢から覚めた。何だかじっとしていられなくなった私は、まだ薄暗いセルビナの町を飛び出した。 |
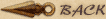 |
