|
ラテーヌ高原には、旅人の行く手を阻む地裂や起伏が目立つ。そこを這うようにしてめぐる道も少々複雑だ。土地勘がない私は、案の定迷ってしまったが、構わずあてずっぽうに進んだ。するとその先には、ほの暗い洞窟が口を開けて待っていた。 どこかで目にしたことがある風景だ。私は記憶の奥底を探った。逸る気持ちを抑えながら、地図を広げた。 その場所はまさしく私の尊敬するエルヴァーンの冒険家、かのオルデール卿の名を冠するオルデール鍾乳洞だった。そう、100年以上も昔に彼が踏破して、後世に地図を遺したという魔窟だ。 少年時代の私と兄は、伝記を読んで以来、オルデール卿にすっかり夢中になった。鍾乳洞の入口の様子も、書物の挿絵か何かで見たのだろう。 オルデール鍾乳洞は、私たち兄弟にとって憧れの場所だった。しかし、いざ薄暗い内部をのぞき込んでみると、途端に鼓動が早くなる。行く先の危険を思い躊躇したその時、冷たく湿った風が私の背中をそっと押した。"前へ進め"と。 私は深呼吸をしてから、勢いよく鍾乳洞へ足を踏み入れた。かつてオルデール卿もそうしたように……。 この鍾乳洞は「人体洞」の異名を持つ。人間の臓腑によく似た複雑な構造ゆえだと言われている。 |
地図を持っていなかった私は、内部の輪郭を丁寧に記録しながら着実に奥へと向かった。清浄な冷たさに満ちた空間が、どこまでも続いていた。 数時間は歩いただろうか。ある場所で偶然古びた木箱を発見した。冒険者たちが必死で探していると聞いてはいたが、実物を見るのは初めてだ。木箱に近づこうとした時、向かい側から響く女の叫び声に遮られた。 |
 |
| 私はほとんど反射的に数歩下がった。駆け寄ってきた若いエルヴァーンは、目の前にひざまずくと、こう言った。 「待って! お願いです! どうかその木箱を……お譲りください」 随分と変わった頼み事だ。とはいえ、拒む理由もないので応じることにした。中身は何であれ、私のような風来者には無用の代物なのだろうから。 彼女は礼を述べて木箱を開けたが、望みの物ではなかったらしく、小さなため息をもらして立ち上がった。そして、オルデールの姓を名乗った。私は耳を疑った。 私と兄がオルデール卿に夢中だった時分、その末裔の一族に令嬢が生まれたという噂が流れていた。だが、時を経てこの地でその人と出会うことになるとは。 令嬢は静かに話し始めた。存亡の危機に直面しているオルデール家のこと、そして彼女が一族を救うために探し求めている幻の財宝のことを。 「オルデール卿が発見した金鉱などは、あなたのおじい様の代までに採掘し尽くしてしまったはずでは?」 「確かに、何もかも果てました。ここに眠るはずの遺産を除いては」 令嬢は、こう続けた。オルデール卿は亡くなる数日前、ごく身近な人物にだけ鍾乳洞に隠した財宝のことを語った、と伝えられている。だが一族の記録にも残されていないため、真偽のほどは定かではない、と。 「今や斜陽の一族とささやかれる我がオルデール家を、何とかして救いたいのです。でも、わたしにはこうして幻を追うことくらいしか……」 |
 |
「それでこんな危険な場所を探検とは、さすがオルデール家のご令嬢だ。けれど、おひとりでは辛いはずです」 ひとすじの涙が令嬢の頬を伝った。 「……どうかお助けください。今や明日の糧にも窮する我が一族に、希望と誇りを取り戻させてください」 「敬愛するオルデール卿に誓って」 |
|
その時の私には、何の迷いもなかった。オルデール卿の遺産など、既に存在しないのかもしれない。 そう考えもしたが、真相がどうであれ、オルデール家が没落してゆく様をただ眺めているのは悲しすぎた。それに、少年時代の英雄であったオルデール卿の足跡をたどって隠された遺産を探すことで、彼の魂に触れられるような気もしたのだ。 私たちは、オルデール卿の遺産を探し求めて、さらに奥を目指した。 (前編 完) |
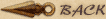 |
