|
敬愛するオルデール卿が後世の冒険家たちへ遺した想いを知り、気持ちを新たにしたKauffmann(カウフマン)氏は、鍾乳洞にしばしの別れを告げて、サンドリア王国を目指した。 朝もやに包まれた東ロンフォールの森で、私はひとり、シュヴァル川を見つめていた。その清い流れに、手製のフライを放つ。鮮やかな黄色の羽根は、生きた羽虫のようにふわりと踊り、川面に舞い降りる。 しかし、感覚の鈍った手では、狙った一点へ糸を伸ばすことなどできなかった。休みなく歩き続けてきた私の疲労は、この時極限に達していた。 あと半日くらい歩けばサンドリアに到着することはわかっていたが、そんな体力も残されていなかった。 柔らかな苔に覆われた地面に寝転んで、ただ泥のように眠りたいというささやかな願いも、ひどい空腹に阻まれた。思い起こせば、鍾乳洞で盗賊の令嬢とバブルチョコを分け合ったのが、最後の食事だった。かれこれ2日以上前の話だ。 |
| そこで私は仕方なく、ボロボロの体に鞭打って、川に泳ぐ魚を狙うことにしたのだ。幸い、手製の釣竿と擬餌は常に持ち歩いていた。 「そのヒカリマス捕っちゃダメ!」 釣り糸を垂らしたまま、ぼんやりしていた私は、突然の怒声に驚き、反射的に振り返った。途端、斧の刃が鼻の先をかすめた。 小さな体に重そうな甲冑、垂れ下がった大きな耳。ゴブリンだ。 |
 |
| 「ああ……悪かった。その、ここが君の縄張りとは知らなかったんだ」 そう言い終えた途端、私は激しい目まいに襲われて、思わずその場に膝をついた。しかし、それが幸いだったらしい。頭上すれすれのところで、ゴブリンの斧がうなりを上げた。 「シュヴァル川のお魚、1匹も渡さない!!」 「そう怒らないでくれ。こっちもこの数日、何も食べて…な……」 さらに、容赦ない一撃を奇跡的にかわした瞬間、世界がぐるりと逆さまになった。 倒れた私の目には、錆びた鉄靴、次いでぴたりと動きを止めた斧、最後に鉄冑の隙間からのぞくギョロリとしたふたつの目玉が映った。 ゴブリンは、その後、何度も私の顔をのぞき込んだり、ひとしきり周囲をうろついたりした。それから、おもむろに私のポーチをごそごそと探り始めると、ありったけのフライやミノーをつかみ取って、一目散に逃げ出した。小さな背中には、不釣り合いなほど大きな釣竿が揺れていた。 (釣り師…か……。もしかして、釣り具が欲しかっただけなのか……) ゴブリンが去ったのを見届けてから、私はそれまで何とか開いていた目をゆっくり閉じた。もう、疲労も空腹もほとんど感じなくなっていた。魂が半分くらい、肉体からずるりと抜け出しているような心地がした。 そこへ、微かな衣ずれの音と共に何者かの気配が近づいてきた。ゴブリンが、とどめを刺しに戻ったのだろうか。重い瞼を開いた私は、思わず息をのんだ。 |
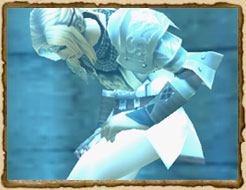 |
純白の衣に身を包んだ乙女が歩み寄ってくる。まばゆい光をまとった姿は、この世の美しさではなかった。ひょっとして楽園からの遣いだろうか。私は、頭の隅で覚悟さえした。彼女は膝をついて座ると、私の体をやさしく抱き起こした。 (参ったな……まさか腹を空かして天へ召されるなんて……。オルデール卿とは大違いだ) 私は、力なく微笑んだ。彼女もまた慈愛に満ちた表情で私を見つめると、はかなげな手をそっと差し伸べた。 |
|
するとその時、やけに香ばしい匂いが鼻の先をかすめた。不思議に思って女を見上げると、その顔はゆっくりと別のものに変わっていく……。私は驚いて、頭を強く振った。 どうやらここで、意識を取り戻したらしい。 目の前にあったのは、他でもないゴブリンの顔だった。 釣り具を奪って逃げたゴブリンが、私の顔をのぞき込んでいたのだ。その小さな手には、私が何よりも欲していたマスの塩焼きが握られていた。 私は、やっと気がついた。 この飢えた旅人のために魚を釣りに行ってくれたのだ。ゴブリンが少々きまり悪そうに無言で勧めてくれた塩焼きを、私は夢中でほおばった。焼き加減も岩塩の振り方も絶妙だ。あっという間に、頭から尾っぽまで平らげてしまった。 「おかげで命拾いしたよ。それに、こんなに旨い塩焼きは、初めてだ」 “彼女”は、とても満足そうに2度ばかり頷くと、足早に去っていった。その後ろ姿は、何だかかわいらしくもあった。 川辺でひと休みした後、私は再びサンドリアを目指した。 森の小道を延々と歩き続けると、やがて夕焼けの中にそびえる城壁の影が現れた。城門には威風堂々と掲げられた緋色の国旗が、突風を受けて帆のようにはためいている。 何もかも、あの頃と同じだった。 |
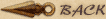 |
