| 宿屋「不死鳥の止り木」の部屋で、しばし休息した私は、昔の記憶をたどって夜の街を散策することにした。ギルドの並ぶ工人通りを北に進んで、ドラギーユ城の地下道を抜けると、見違えるほどきれいになったサンドリア港に出た。 私は埠頭に立ち、さざ波の音を聞いた。かつて悪友たちと通い、日没まで釣りをしていた場所だ。 ここでは、誰の獲物がいちばん大きいだの、釣った魚が消えただので、いつも何かしかの騒ぎが起こったものだった。もう20年以上も昔のことだ。 しばらく夜風にあたっていたせいで少し体が冷えてきた私は、すぐ近くの酒場「錆びた錨」亭で、暖を取ろうと考えた。 飛空艇などなかった昔は、こんな気の利いた店はなかった。確かここは、小うるさい漁師の家で……。 そんなことをぼんやり考えながらカウンターでグラスを傾けるうちに、過ぎた日の光景が、ありありとよみがえってきた。 |
私が留学生としてサンドリアにやって来たのは、確か12歳の秋だった。 まだまだ子供だった私は、父の勧める学問にはまるで関心がなかったが、大きな街での暮らし自体は楽しくてしかたがなかった。 遊び仲間たちも、ほとんどが留学生だった。石造りの築城術を学ぶ者、チョコボの生態と騎乗を学ぶ者、大聖堂で神学を修める者……。 |
 |
| 私たちは、寝食を共にし、夜な夜な理想を語りあった。皆が勤勉だったとは言い難かったが、輝かしい未来を信じて疑わない心は、同じだった。 だが、その翌年、獣人と人間との大規模な戦争が始まり、私たちを取り巻くすべてが変わってしまった。急速に勢力を拡大した獣人軍は、各地で容赦ない略奪と破壊を繰り広げ続けた。 幸いサンドリアの人びとは、堅牢な城塞と鋼の盾のような騎士団とに守られたが、留学生の多くは肉親を、そして故郷までをも失った。 私も、そのひとりだった。 溶けて丸くなった氷が、カランという寂しげな音を立てて、グラスの底へ落ちた。我に返った私は、残っていた酒を、ひと息に飲み干した。 その時、少年とも少女ともつかぬ声が、私をたしなめた。 「おい、そんな飲み方をするな」 顔を上げて背後を振り返ってみても、声の主らしき人物など見当たらない。 「上等な酒に失礼だろう」 めずらしく、酔いが回っているのか。私はカウンターに向き直って、店の主人に冷たい水を頼んだ。すると彼は、顎先で私の足もとを示した。 いったい、いつからだろうか。 そこには、ぴかぴかの鎧に行儀よく収まったタルタルが、私を見上げて立っていた。 その嬉しそうな顔を眺めるうちに、酔いは急速に醒め、世界は鮮明さを取り戻していった。 |
 |
驚いた。彼女は、留学生時代につるんでいた悪友のひとりだったのだ。 「ああ、なんてことだ! まさか、君に会えるなんて……!」 「……よく生きていたな!」 私たちは、その場で抱き合って再会を喜んだ。 店の主人は、ただ黙って、新しいボトルを差し出した。 |
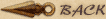 |
