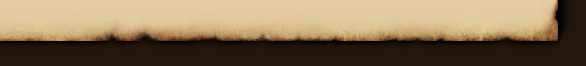|
 |
ゲームに使われているのは、ゴブリンダイスと呼ばれる12面体のダイスだ。
このダイスは、たいていゴブリンたちの手で、わずかに歪んだ形に仕上げられている。そのため特定の目だけが出しにくかったり、振り方次第で狙った目をほぼ確実に出せたりと、1つ1つに異なる癖がある。
ダイスの歪みはゲームに面白味を与えたが、一方で、いわゆるイカサマ行為の横行を招いた。そしていつしか、イカサマ行為は、あからさまな場合を除いて黙認されるようになった。本職などは、互いの手技の華麗さで競い合っているくらいだ。
かく言う私にも、行きつけの酒場の常連客とイカサマ勝負に熱中していた時代があった。
私の師は、酒場の親爺だった。狙った目を出す方法から、ダイスを改造する方法まで、彼はあらゆるイカサマに通じていた。
最後に親爺と勝負した晩から長い月日が経っていたが、私の右手はダイスの感触をまだ忘れてはいなかった。
「また、しくじったか! 今のは上がれると思ってたのに!!」
そう叫んで頭を抱えた右側のミスラに、正面のミスラが言った。
「ちょっと、これで連続5ゲーム目よぉ? こんなに場のチップを増やしたら、次に上がる誰かのひとり勝ちになっちゃうじゃないのぉ」

テーブルには、金銀のインゴットが小山のように積み上げられていた。3人は、故意にゲームを流し続けているに違いなかった。そうやって極限まで賭け額をつり上げたところで3人のうちの誰かが上がり、一気に奪い取っていくつもりなのだろう。
ゲームそのものは、親から順に自分のダイスを順に振り、4人の出した目の組み合わせで規定の役を狙う、という単純なものだ。
最初に、子の3人が同時にダイスを振る。そこで出た3つの目を活かし、まずは親が役の完成を狙う。そこで何の役もできなければ、あとの3人
も順に自分のダイスを振り直して役を狙う。4人目まで何の役もできなければ、そのまま2巡目に突入。
しかし、誰も上がれずに3巡した場合、そのゲームは流れ、賭けられていたチップはすべて次に持ち越されてしまう。あっという間に賭け額が膨れ上がる仕組みになっているのだ。
「今度の親は、お兄さんかな〜?」
親は、勝てば他の3人から賭け額の2倍を取れるが、負けたら賭け額の2倍を支払うはめになる。私にとって、この1ゲームが正念場であることは明らかだった。
最初に3人が出した目は、役など作りようもないくらいバラバラだった。もちろん、私の上がりを阻むためだ。その代わり、1巡目は彼女たち自身も上がれずに終わった。
2巡目は、私から順に「6、8、9、10」を出して終わった。4人目の女が、「7」を外して上がり損ねたのだ。そして、3巡目。いよいよ最後の1投が回ってきた。
ここで自分のダイスの目を「6」から「7」に替えられれば、勝てる。ただし、これまで一度たりとも奇数の目を出していない私の黒いダイスが「7」を出せるなら、の話だが。
明らかに形勢は不利だったが、ここで外したら最後、ミスラたちは、どんな手を使ってでも、3人のうちの誰かを上がらせようとするはずだ。
ならば、先に上がるしかない。
覚悟を決めた私は、黒いダイスを拾い上げつつ、こう宣言した。
「悪いが、ここは勝たせてもらう」皆の視線が私の顔に集まった。
その瞬間を待っていた私は、すかさず黒いダイスを投げた。力強く転がりはじめたダイスは、やがてテーブルの中央で音もなく止まった。
……出た。狙いどおり「7」だ。一瞬の沈黙の後、周囲の見物客たちがどっと沸いた。ミスラの3姉妹は一斉に立ち上がった。
「な、7ですって〜!?」
「こんなのおかしいわぁ! この男、絶対イカサマしたのよぉ!!」
「あたしらのシマでいい度胸だ……。望み通り串焼にしてやるよ!!!」
尻尾を逆立てて凄んだ3人が同時に指笛を鳴らしたかと思うと、用心棒らしきゴブリンが瞬く間に私を取り囲んだ。交渉の余地がないとわかれば、一刻も早く退散するしかない。
私は、用心棒たちを引き連れたまま、見物客の輪に突っ込んだ。すると、腕っ節の強そうな男たちが、待ってましたとばかりにゴブリンにつかみかかり、取っ組み合いを始めた。やはり、彼らは騒ぎに飢えていたのだ。すぐに部屋じゅう乱闘騒ぎとなり、あちこちで雄叫びや歓声が上がった。
その混乱に乗じて部屋を飛び出した私は、もと来た通路を一気に駆け抜けた。先を見ると、見張りのゴブリンに閉ざされたはずの隠し扉が半分開いていて、1人の女が向こう側から手招きしている。
彼女こそ私にダイスを投げつけたあのミスラであり、ジュノの酒場で勝負に明け暮れた、かつての好敵手でもあった。

「あなたにしては、派手にやったものね 」
私が外に出ると、彼女はすぐに重い扉を閉ざした。数年ぶりとはいえ、再会を喜ぶ暇などない。私たちは抜け道を走り、洞窟の出口を目指した。
「本当に助かったよ。君が投げてくれたこいつのお陰で、あの3人に骨までしゃぶられずに済んだ」
走りながら、私は「7」を出した黒いダイスを彼女に投げて返した。
「あの3姉妹の目を盗んでダイスをすり替えるだけでも難しいっていうのに、きっちり狙った目を出すとは、さすがね。何度もあたしを負かしてくれただけのことはあるわ」
「そんなのは昔の話だ。今の君には、きっとかないやしないさ」
少し息切れしてきた頃、ようやく出口の光が見えてきた。幸い、追手の来る気配はなかった。
「ここまで来れば大丈夫だ。君の方も怪しまれないうちに戻ってくれ」
そう促すと、彼女は私を見ずに言った。
「わざわざ戻る理由なんてないわよ。もう十分に稼がせてもらったことだし。それより、久しぶりにジュノに戻って、マスターの店に顔でも出そうかと思うんだけど……」
「……あの親爺、きっと喜ぶだろうな。よろしく伝えてくれよ」
「なによ。相変わらず、つまんない男ね」
彼女は、あの頃と同じようにあきれ顔で笑った。
|
 |
|