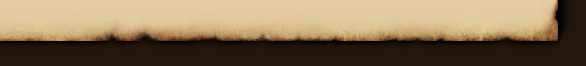|
 |
サルタバルタで迎えた朝は、思いのほか冷え込んだ。肌寒さで目覚めた私は、くたびれたクロークを羽織り、ザンビビ川のほとりを散歩することにした。
澄んだ水の中を覗いてみると、時おり魚たちの影が見え隠れする。童心に返って、魚探しに没頭していたその時だ。すぐ近くから何者かのうめき声が聞こえてきた。
「う……あ……」
私は喉から心臓が飛び出るくらい驚き、声にならない悲鳴を上げた。慌てて振り返ると、足元の茂みに人が倒れている。エルヴァーンの女だ。
顔色は少し青ざめていたが、見たところ外傷はなさそうだった。
「どうした? しっかりするんだ」
乾いた唇が、かすかに開いた。
「み……ず……」
女は、川の流れを指し示すように腕を伸ばした。
人形のように力の抜け切った体を支えて起こしてやると、女は赤ん坊のように地面を這って川辺にたどり着いた。そして、水面に顔を近づけたかと思うと――、そのまま流れの中に頭ごと突っ込んでしまった。
10秒、20秒……。30秒経っても微動だにしない。心配になって肩を揺すると、女は、ざばりと頭を上げた。
「……もう平気。酔いは醒めたわ」
何のことはない。ただの酔っぱらいだったのだ。
脱力した私に、彼女はこう言った。
「迷惑をかけたついでに、もうひとつお願いしたいの。ノルバレンという地方に、エルヴァーンたちの眠る墳墓があるそうね。そこへ行く道を教えてくださらない?」
その瞳は、別人のような鋭さを取り戻していた。
女が言っているのは、エルディーム古墳などに代表されるコヴェフ墳墓群のことだろう。私は、彼女の持っていた地図にルートを記し、途中の難所や近道についても、できる限り詳しく説明した。
「余計なことを言うようだが、あの辺りの墓は、どこも物騒だぞ」

「ちょっと覗いてくるだけだから、平気。でも、ご心配ありがとう」
女は、まだ濡れている髪を両手でかき上げながら、しっかりとした口調で答えた。
「……父の眠っている場所を、ひと目見たいだけなの。そのために、はるばる南方の島から船で来たのよ」
女の父親くらいの世代で、あの場所で亡くなったエルヴァーンということは……。
もしやと思った私は、思い切ってこう尋ねた。
「失礼だが、もしかして君の父上は20年前の大戦で?」
女は、荷造りの手をぴたりと止めた。
「いかにも、その通りよ」
ああ、やはり……。私は、言葉を呑んだ。
「貴方も、噂に聞いたことはあるでしょう? 大戦で犠牲となった西方の小国のことを。私の一家は、その国で侯爵家にお仕えしていたの」
「…………」
「母は、生後間もない私を抱いて南方の島へ逃れ、ひたすら父を待った。でも父は、終戦間際に亡くなっていたのよ。最期まで忠義を尽くして主君をお守りしたんですって。……と、失礼。一方的に話しすぎたようね」
「いいんだ。そんなことより、同郷の友に出会えたことに感謝せねば」
女は顔を上げ、目をしばたいた。
午後になると、空は鮮やかな青色に染まった。上空の雲は羊の群れのようにゆっくりと流れ、いつの間にか見えなくなった。
小川のほとりに腰を下ろした私たちは、今はなき故郷の話をしていた。
「私の家の側には、川が流れていたんだ。こういう天気の日には、よく兄と遊びに出かけた」
私は、消息を絶っている父と兄のことも話した。成り行きだったとはいえ、自分から誰かに過去の話をするのは、おそらく初めてだった。
「そう……。どんな川だったの?」

母親が過去のことを話したがらないせいで、故郷のことをほとんど知らずに育ったという女は、どんな些細なことでも知りたがった。
「この川より、ずっと大きかったな。もっとも、私が子どもだったからそう感じただけかもしれないけれど」
両膝を抱えて私の話に耳を傾けていた女は、川面の一点を見つめたままつぶやいた。
「私は、祖国の風景を知らない。父の顔も覚えていない。けれど、その国に生まれたこと、それに父の娘であることを、ずっと誇りに思って生きてきた」
その時、乾いた風が吹き抜け、川面を鏡面のようにきらめかせた。私は、思わず目を細めた。
「お酒が好きなのも父の血よ。変なところばかり父譲りなの」
「そいつは、私も同じだ」
女は静かに笑ったかと思うと、不意にこんなことを尋ねてきた。
「ねえ、エルシモ島に行ったことは?」
「いや。話に聞いたことしかない」
「私と母が暮らしているノーグという港には、あの国から落ち延びた人が何人も暮らしているの。だから、貴方のご家族の手がかりも……」
そう聞いた途端に、様々な感情が怒濤のように押し寄せ、私の胸を苦しめた。
もしや、父と兄もノーグに? いや、もう期待してはいけない。この20年間、さんざん裏切られてきたではないか……。
自らを戒めるために、私は小さく首を振った。
夕暮れ時、女と私は、それぞれ北と南を目指して出発することにした。彼女は、別れ際に右手を差し出してこう言った。
「貴方に出会えてよかった。いつかまた、話を聞かせてほしいわ」
「君とはまた会える気がするよ。旅先の街か、あるいは……」
「あるいは、祖国タブナジアで!」
私たちは、固く握手を交わした。
女の瞳は、いつか見たタブナジアの夕日のように、強く美しく輝いていた。
|
 |
|