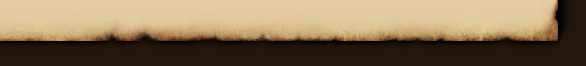|
 |
東サルタバルタのノンピピ川を越えた翌日、遂にミンダルシア大陸最南端の都市ウィンダスにたどり着いた。
もう、5年も昔の話になるだろうか。とある傭兵部隊の一員としてギデアスで野営していた私は、底をつきかけた隊の食料を調達するために、一度だけこの街を訪れたことがあった。
サンドリアやジュノとはまるで違うのどかな街の様子に少なからず興味をひかれたが、優雅に観光できるような状況であるはずがなく、その日のうちにとんぼ返りしたと記憶している。
今度こそウィンダス中を見て回ろう。ずっと楽しみにしていた私は、まず森の区の散策からはじめた。手の院ではカーディアンと会話し、ミスラの集落では族長の姿を垣間見た。
牧場では、ダルメルたちに名前がついていることを知った。森の区をひと巡りした後は、星の大樹を拝むために石の区へ――。そのはずが、気づいた時、私は港に出ていた。
迷ったついでに漁師ギルドでも覗いてみようと、その場で地図を広げた途端、何かが脚に絡みついてきた。
「!?」
わけのわからないまま視線を下に移すと、右脚にタルタルの娘が力一杯しがみついている。いたずらだろうと思って、たしなめようとした矢先、娘は歓喜の声を上げた。
「おひさしぶりです! またお会いできるなんて、わたし……!」
もしかすると古い知り合いだろうか。私は上体をひねった姿勢のまま、娘を見つめた。尖った耳に、涙で潤んだつぶらな瞳。子犬のような鼻。心当たりがあるような、ないような。さて、どうしたものか……。
「その優しい眼差し。ちょっと寂しげな笑顔。なにもかもあの日のままなのですね。うれしい……」
そう言って、娘は私の脚に頬をすり寄せてくる。その時、既に私は彼女のペースに巻き込まれていた。
「いや、あの日って――」
否定しようにも、甲高い声が私の言葉を遮る。
「あっ。あそこに見えるのが、あの時の防具屋ですよ!」

満面の笑みで見上げる娘は、まるで幼子のように私の上着の裾をつかんで放さなかった。私の戸惑いなどよそに、彼女はもう一方の手で桟橋に立ち並ぶ店を指し示した。
「じつは店番の仕事は少し前にやめてしまったのですが、10年前にお預かりしたクロークは今でも――」
「待ってくれ」
やっとの思いでひと言ねじ込んだ私は、娘の目の高さに合わせてしゃがんだ。
「あの、残念だけど人違いだと思う。なかなか言い出せなくてごめんよ」
私がウィンダスを訪れたのは5年前だ。決して、10年前ではない。
「そん……な……」
娘は、しばし立ちつくしていたかと思うと、たいそう気落ちした様子で去っていった。
その後、私は漁師ギルドを見物する予定を変更して、桟橋の防具屋へ向かった。何だかんだ言っても、やはり娘の話が気になっていたのだ。
防具屋で店番をしていたのは、彼女と似た顔をしたタルタルの少女だった。少女に10年前のことを尋ねてみたところ、興味深い答えが返ってきた。当時の店番で、少女と言える年頃だったタルタルといえば、自分の姉に違いないというのだ。
「おねえちゃんは、もうすぐおよめさんになるのですっ。それでクママが、かわりにお店やさんのお手伝いをはじめたのですっ☆」
少女は誇らしげに言った。その隣で客の相手をしていた店主も、後から加わって、少女の姉について話を聞かせてくれた。
あの娘は、婚約者に出会うまでの間、ある青年のことをずっと想っていたという。10年前、彼女が初めて店に立った日の、初めての客だったそうだ。店主は、その青年の顔までは覚えていないが、彼がヒュームだったことは確かだと語った。
たまたま私が、その青年に少し似ていたのだろう。とはいえ、何だか娘に悪いことをしたような気がした。
私がこの港に来なければ、彼女は悲しい思いをせずに済んだのだから。
結局その日は、早々に街の見物を切り上げてしまった。どうも、そんな気分ではなくなってしまったのだ。
夕食も取らずに宿屋のベッドに倒れ込んだ私は、いつの間にか眠りについていた。その夜は、久々におかしな夢を見た。
「やあ、お嬢さん。ここは素敵な街だね」
夢の中で、私はタルタルの少女に随分なれなれしく声を掛ける。頬を薔薇色に染めた少女が、私を見上げてこう言う。
「いっ、いらっしゃいませ!」

どこか見覚えのある店構えだ。昼間立ち寄った港の防具屋にも見える。
あれこれと世間話をしながら、私は トランクから衣類を取り出して次々とカウンターに並べていく。少女は緊張した面持ちでそれらを1着ずつあらためて買値をつけていく。
最後の1着をカウンターに広げたところで、私は片肘をついてしばし考え込む。少女は心配そうな顔をして、こちらを見つめている。
不意に、私が口を開く。
「……やっぱり、こいつを金に換えるような真似はしたくないな。ねえ、お嬢さん。このクロークはキミにプレゼントするよ」
「いっ、いけません、お客さま! こんな上等なお品を!」
「いいんだ。確かに苦労して手に入れた代物だけど、残念ながらこの先は要らなくなりそうだからさ。ほら、キミの琥珀色の瞳によく似合う」
少女は口をぱくぱくさせながら、受け取った朱色のクロークの重みによろめく。それを見た私は、明るく笑いながら防具屋を後にする。
その笑い声に、はっとして目覚めた。
違う。私は、あんなふうに笑ったりしない。あれは私ではない。
私によく似た別人なのだ。
「ああ、まさか…………」
鉛のように重い体を起こした私は、鈍い痛みの走る頭を両手で抱えた。そして、そのまま朝を迎えた。
|
 |
|