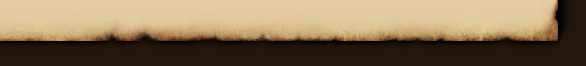|
 |
目の前で気怠そうに頭をかきむしっているタルタルの男――クビラウンビラ号の船長は、私を歓迎していない。それだけは、明白だった。
彼はひと言も発することなく、甲板の隅に脱ぎ捨ててあったサンダルを片方ずつ蹴り上げて表に返すと、そこに日焼けした足を突っ込んだ。
気がつけば、辺りはやけに静まりかえっている。聞こえるのは、船を揺らす波の音と風の唸り声だけだ。少年も海鳥たちも、こういう時は、おとなしく様子を窺うつもりらしい。
「……無理を承知で、あなたに頼みたい。エルシモ島のノーグまで、船を出してもらえないだろうか?」
単刀直入に切り出した私に、彼は低い声で切り返してきた。
「寝ぼけたことを言うな」
背格好こそ他のタルタルと何ら変わらないが、オレンジ色の防塵眼鏡の奥に見え隠れする眼光は、さながら鋭利なナイフのようだ。
「だいたい海賊どもの根城なんかに何の用だ。……まさか、骸どもに骨までしゃぶられにいくわけじゃないよな」
彼の一瞥に、ナイフの切っ先が自分に向けられたような錯覚を覚える。
「ある男を捜している。大切な預かり物を届けたいんだ」
そう返した途端、彼は私の手からするりとスカーフを抜き取って広げた。その直後に、左の眉が吊り上がった。
「何だ、この汚ねえ字は。む……」

「紹介状だ。あなたをよく知る女性が書いてくれたものだ」
「……そうらしいな」
横から覗き込む弟を気に留める様子もなく、船長は滲んだ文字を食い入るように読みはじめた。ところが、ある箇所で突拍子もない声を上げた。
「なっ、ん、だ、とーー!?」
機を窺っていた少年が、すぐさまスカーフを奪い取り、嬉々として文面を読み上げた。
「なになに?“もうじき嫁ぐ幼なじみへのはなむけだと思って、頼みをきいて。これが最後だから……”こ、これってつまりクママんちの姉ちゃんがケッコンするってこと〜!?」
「……知るか!」
あの娘との間に何かあったのか、船長は少なからずショックを受けているように見えた。
「兄ちゃん、元気だせよ〜。きっと、ほかにもいいひといるって〜」
「だから兄ちゃんって呼ぶな!!」
それから船長は、ひとり言でもつぶやくかのように、幼なじみの娘とのことを語りはじめた。
ウィンダスで生まれた船長兄弟は、10年前まで姉妹の隣家に暮らしていた。やがて彼らはマウラへ越してくることになったが、野菜を仕入れる目的で定期的にウィンダスへ船を出すようになってからは、姉妹と顔を合わせる機会もできたという。
それなのに船長は、あの娘から肝心なことを聞かされていなかったのだ。彼は、ひと月前に会った時も、いつものように憎まれ口を叩いて別れてしまったと言って、肩を落とした。
「……で? どうしてあいつの結婚祝いに、あんたを船で送らなきゃならないんだ?」
そう尋ねてきた船長に、ウィンダスで娘と知り合った経緯を説明すると、彼はボサボサの頭を両手で抱えた。
「ちっ、そういう事情か。あいつめ、勝手に俺を巻き込みやがって」
「まぁまぁ。初恋のカノジョにおねがいされちゃ、さすがの兄ちゃんもことわれないってことで――」
無言の圧力で弟を制した船長は、私の方に向き直って言った。
「俺は、ノーグに近づくのは御免だ。うっかり潜入して、おっそろしい目に遭ったことがあるものでな。それと、この船でカザムに入港するのも駄目だ。ミスラの役人が面倒なんだよ。それくらい、わかるだろう?」
彼の言うことは、もっともだった。兄の夢を見た晩から、私はすべてが向かうべき場所に向かって動きだしたかのように感じていた。けれども現実は違う。それだけのことなのだ。
ふたりへの非礼を詫びて船から降りようとした時、船長が言った。
「……だから、あんたにはカザム沖で仲間の船に移ってもらう。あとは自力でどうにかするんだな」
「……ああ、それで十分だ……!」
喜びのあまり、私は彼の手を取った。その小さな手は意外なくらい骨張っていて、そして温かかった。
「勘違いするな。別にあんたのためじゃない」
私の手を振り払って薄く笑った彼は、朝焼けの空を仰いで叫んだ。
「ヤロウどもー! 3分後に出航するぞー! さっさと錨を上げろーー! 帆を張れーー!!」

「さ、3分〜!? そんな、むちゃくちゃなぁ!だいたいヤロウ“ども”
なんてカッコつけたって、3人しか乗ってないじゃないかよ〜!」
文句を言いつつも、少年は出航の準備に取りかかっていた。私は、慌ただしく駆け回る彼を呼び止めた。
「なあ、錨は私に任せてくれ。ほら、君にはちょっと重いだろう?」
「へ……」
彼は目をしばたくと、なぜか返事もせずに走り去り、勢いよくマストによじ登っていった。少年が帆を広げる様子を下から見守りながら、船長がこう言った。
「なんだ、もう気づいてたのか」
「何の話だ?」
錨を引き上げながらそう聞き返した時、にわかに強い海風が吹いてきた。
「そりゃあ、俺のかわいい――」
ふと、頭上に目をやると、まさにその瞬間、マストにしがみついていた少年の帽子が海風に奪われていった。
「妹のことさ」
「……!」
マストの上では、金糸のように輝く長い髪がたなびいていた。
「よーし! 出航だーー!!」
いつの間にか舵を手にしていた船長が、威勢のいい声を上げた。まるでその合図を待っていたかのように、追い風を受けて膨らんだ帆が、ひときわ大きな弧を描いた。
小さなクビラウンビラ号は、海鳥の群れを引き連れて、意気揚々と走り出した。
|
 |
|