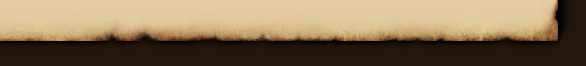|
 |
蒸し暑さのあまり、私は目覚めた。薄暗い部屋の片隅で、小さな灯火が揺れているのが見える。背中一面で、堅い床の感触を感じる。
ここはクビラウンビラ号の船倉だ。マウラを出港して、まる4日が経とうとしている。これまで順調に帆走を続けてきた船は、前日の夕方に早くも目的地付近に到達していたため、洋上で錨泊して朝を待っていた。
狭い船倉のいちばん奥からは、少年――もとい少女の小さな寝息が規則正しく繰り返されている。ということは、まだ夜は明けていないらしい。にもかかわらず、入口そばの寝床には、人の気配がない。
もしかすると船長は、一睡もせずに見張りを続けているのだろうか。私は、彼に見張りの交代を申し出ようと考え、静かに起きあがった。
常夜灯の心許ない明かりの中、甲板へ続く急な階段を上り、小さなハッチを開く。すると、どこからともなく人の声が聞こえる。甲板に首だけ出した状態で様子を窺えば、そこには月明かりに照らされた船長の小さな影。彼が鼻歌でも歌っているのか。
後ろから船長に声をかけようとした時、不意に夜風が止んだ。その途端、彼の声がはっきりと聞こえてきた。
「――ああ、もうとっくに海の上さ。――何? ――あのなあ、謝るくらいなら最初から頼んでくるなって! ――だから、お前はそこで船旅の安全でも祈ってればいいんだよ」
ひとり言ではない。どうやら彼は、リンクパールで会話をしているようだった。そのつっけんどんで、どこかぎこちない物言いから、察しはついた。相手はウィンダスの娘だろう。

「――それより、あれだ。よかったじゃないか。――いや、だから、例の話さ」
出るに出られなくなってしまった私は、船倉に引き返すことにした。
「――おい! 何だ!? ――どうしてお前が、そこで泣くんだよ……」
うろたえる彼の言葉を、やるせない思いで聞いたのを最後に、私は内側からそっとハッチを閉めた。
「お、き、ろーー! このネボスケどもーー!!」
よく通る声が、船倉いっぱいに響いた。驚いて飛び起きた私は、低い天井に勢いよく頭をぶつけた。笑い声の聞こえる方を見れば、ハッチから船長が顔を覗かせている。彼の後ろには、日の光があふれている。
前の晩の記憶をたどっても、船倉へ戻って横になったところで、曖昧になってしまう。不覚にも、あのまま眠ってしまったのだ。
「……すまない!」
私は、船長に借りていた肌掛けを大急ぎでたたんで彼の寝床に戻した。
ハンモックから飛び降りた少女は、寝ぐせのついた長い髪を手早く結ぶと、急な階段をすたすたと駆け上っていった。
彼女が甲板に飛び出していった直後、船長が再び顔を覗かせた。
「おい、お客さん。あんたはここで乗り換えだ。早いところ、荷物をまとめて上にきてくれよ」
逆光のせいで表情までは見えなかったが、その声は意外にも明るかった。
ちょうど荷造りを終えた時、私は甲板の様子がおかしいことに気づいた。荷物を担いで階段を駆け上がると、船長が必死の形相で舵柄を手にし、大声を上げている。マストの上では、彼の妹が何やらわめいている。
彼女が指さしている方を見て、私はすべてを理解した。別の船が、300ヤルム後方まで迫っていたのだ。
「うわわわっ! 兄ちゃん、まずいよ! このままじゃ船尾に追突されちゃうって〜!!」
少女が悲鳴を上げた。赤い帆をかけたその船は、逆風を切るようにジグザグに走り、なおも接近してくる。
「あいつ、また遊んでやがるな……。この風の中、たいした腕だ! !」
そう言って、船長が大きく舵を切った瞬間、赤い帆の船も急旋回して減速した。そうして、2艘の船は、すんでのところで接触を免れた。
「おいおい! 勘弁してくれよ!」
船長が、額の汗を拭って叫んだ。おそるおそる2艘の間を覗き見れば、そこにはわずかな隙間しかない。

「あー、やだやだ。なんて肝っ玉の小さいオトコなのかしら! 」
その高い声を耳にした私は、反射的に顔を上げた。隣に歩み寄ってきた船長が、声の主を顎で示して言った。
「……見ろよ。あれが、ゴールデンボニート号の船長様だ」
黄金の鰹――。漁船なのか、貨物船なのか、あるいは運び屋なのか。 一切は不明だったが、向こう見ずで豪快な操縦に、ぴったりな船名だ。
ところが、目の前に立っている船長と呼ばれる人物は違った。たとえるなら、流行の服に身を包み、ジュノ下層あたりを歩いていそうなヒュームの娘。どう見ても、猛スピードで海を泳ぎ回る鰹のイメージとは、かけ離れているのだ。
「どいてー! 当たるわよー!」
娘は、もやい綱を手に取って振り回しはじめたかと思うと、その一端をクビラウンビラ号めがけて勢いよく放り投げた。
「なかなか刺激的だろう?」
もやい綱を拾い上げて船尾に括りつけながら、船長は皮肉っぽく笑った。
その時、再び高い声が響いてきた。
「ねえー、どれなのー!?“エルシモ島のどこかに放り投げてきてほしい荷物”っていうのはー?」
「あ、こっち、こっち〜!」
するするとマストから降りてきた少女が指し示したのは、やはり私だった。ヒュームの娘は、まるで朝市で魚の品定めでもするかのように、私をじっと見て言った。
「ふーん……。まさか、あぶない荷物じゃないでしょうね」
私は、思わず肩をすくめた。
「そんなんじゃないさ。ただ、できれば天地無用でお願いしたいな」
一瞬の沈黙の後、3人はカザムにまで届きそうな声を上げて笑った。
仕方なしに、私も一緒になって笑うことにした。
|
 |
|