|
|
「そのままこっちへ走るんだ!」 30ヤルム先に少女の姿が現れた。 大羊に追われて走り続けてきた少女は、荒い呼吸を繰り返すのが精一杯で、頷くことすらできないようだった。ただ、その瞳だけは必死の思いで助けを求めているように見えた。 少女を先頭にして、野生の大きな雄羊と数頭の牧羊が連なっていた。その一群が迷わず自分のもとへ突っ込んでくる様子は、何だか壮観だった。私は剣を抜いた。 |
 |
| 「……あの時あなたの声が聞こえなかったら、わたし、逃げるのをやめてしまっていたかもしれません」 少女はそう言うと、雨に濡れた草の上にぺたりと座り込んだ。 倒した羊たちから得た良質の毛皮を大雑把にまとめながら、私は少女の話を聞いた。その声や話し方には、町娘とは違うおおらかさがあった。 少女はラテーヌやロンフォールで牧羊を営む一族の娘だった。まだ羊飼いの仕事を始めたばかりで、失敗続きの毎日らしい。この日もうっかり野生の雄羊に近づいてしまい、逃げ回るうちに自分の羊までもが一緒になって襲ってきたというわけだ。 放牧が盛んなこの辺りではよくある話で、新聞に載ることもないのだ、と言って少女は素朴な笑顔を見せた。 それに応えるように、雨が上がった。流れる雲が遥か彼方に消えると、少しすみれ色がかった青空が広がった。すぐ横に座っていた少女が声を上げて立ち上がったので、ふと顔を上げると、少女は遠くを指差していた。私は目を疑った。 虹だ。薄い絹のように透き通った七色の橋が、大空にふわりと掛けられていた。 そういえば、どこかの酒場で聞いたことがあった。ここは「虹の高原」という名でも呼ばれることを。 |
 |
「ザルクヘイムの羊飼いは、昔から信じてきたんです。虹に願ったことは女神様が叶えてくれるって……」 少女は胸元のペンダントを握りしめ、私の旅が実り多きものになるようにと、小さな声で祈ってくれた。 私は、見習羊飼いの安全と幸せを、彼女には内緒で願うことにした。 |
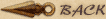 |
