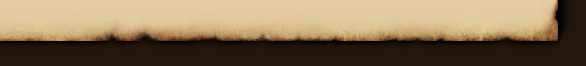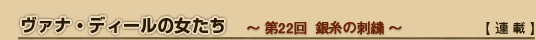 |
 |
ベッドの上でうずくまっていた私に夜明けの訪れを知らせてくれたのは、小鳥たちのさえずりだった。顔を上げると、鎧戸の隙間から外の薄明かりが見えた。
綿の肌掛けにくるまったまま、あれこれと思い悩むこと2時間。ようやく心を決めた私は、床に投げ置いてあったブーツを履いて、肩に荷物を担ぎ上げた。
勢いよく部屋の扉を開け放った瞬間、真新しい朝の光が洪水のように流れ込んできた。私は胸いっぱいに息を吸ってから、宿屋の階段を一気に駆け下りた。
目指すは、港の防具屋。それというのも、店番の少女に彼女の姉の居場所を尋ねるためだ。ウィンダスを発つ前に、もう一度あの娘に会いたい。ヒュームの青年について聞きたい。
その一心で、私は走った。
「君! お姉さんは今どこに!?」
防具屋に駆け込むやいなや、私は店番の少女に尋ねた。彼女は、ぽかんと口を開けて私を見上げていた。
「ああ、ごめんよ。実は、もう一度君のお姉さんに会って、例の思い出のひとについて詳しく聞きたくてさ。その、ひょっとするとそのひとは私の知り合いかもしれないんだ」
私の説明をどう解釈したのか定かではないが、少女は前日と同じ調子で答えてくれた。
「おねえちゃんは調理ギルドやさんにいるとおもいますっ。きょうは、お料理教室の日ですから☆」
調理ギルドは、宿屋の目と鼻の先にあった。来たばかりの道を戻るはめになるとは、ついていない。私は、上着を脱いで再び走りはじめた。桟橋の中ほどで何気なく後ろを振り返ると、少女と店主が飛び跳ねて手を振っているのが見えた。私も大きく両手を振って返した。
いざ調理ギルドを訪ねてみると、娘の姿はなかった。エルヴァーンの料理人に尋ねたところ、彼の方が慌てはじめた。ついさっきまで後ろで野菜の皮むきをしていたはずなのに、いなくなっているというのだ。ならば、まだ遠くへは行っていないはずだ。私は外へ出て辺りを捜し回った。
調理ギルドの近隣をぐるりと一周した頃には、すっかり息が上がっていた。宿屋を飛び出した時から、ほとんど休みなく走り続けていたせいで、両膝もがたがただった。

もう一度だけ調理ギルドを覗いたら、今日はあきらめよう。辺り一面に咲く、名も知らぬ薄紅色の花を眺めながら、そんなことを考えていた時、見覚えのある帽子と小さな背中が目に飛び込んできた。
水辺にたたずみ、辺りに咲き乱れる花々を見上げるそのひとは――。
やっと見つけた。あの娘だ。私は、まだ激しく鼓動している胸を押さえながら、彼女の方にゆっくりと歩み寄った。
「……やあ。捜したよ」
よほど驚かせてしまったらしい。娘は私の姿を認めると、ぽかんと口を開けてその場に立ちつくしていた。その顔が防具屋の妹と同じであることに気づき、私は思わず微笑した。
「花嫁修業はどうした?エスケープしたのかな?」
図星だったらしく、娘は頬を薔薇色に染めてうつむいた。私は彼女の隣に腰を下ろした。
「君に聞きたいことがあるんだ。それから、聞いてほしいことも」
私は10年前の出来事を確かめるために、前の晩に見た夢のことを話しはじめた。夢の舞台から登場人物たちのやり取り、そして台詞に至るまで、思い出せる限りを語った。娘は手足をばたつかせて言った。
「すっ、すごいです!! 10年前のわたしたちを、どこかで見ていらしたみたい!」
聞けば、私の夢は当時の出来事を、そっくり再現しているのだという。
やはり思った通りだった。不思議な夢を見たのは、これが初めてではない。だから彼女の言葉を受け止めることはできる。では、10年前に防具屋を訪れたヒュームの青年とは何者なのか? それだけは、依然として謎のままだった。
考え疲れた私は、仰向けに寝転んだ。ぼんやり空を眺めていると、舞い降りてくる花びらが時おり頬にかかる。

うららかな昼下がりに散り急ぐ薄紅色の花。そのはかない美しさに心を奪われていると、頭の中に突然あの笑い声がこだましはじめる。底抜けに明るい、彼の笑い声が……。
「もしかして、あなたはあの方をご存じなのですね?」
娘の言葉に面食らって、私は体を起こした。
「……さあ、どうかな。そうだったらいいけれど」
私は彼女の正面に座り直し、大戦のこと、父と兄のことを話した。娘は、ただ黙って私の話に耳を傾けていた。
「戦場と化した街で、軍人でも冒険者でもない、ごく普通の親子が生き延びられるものだろうか? ……兄なんて、まだ14だった」
「お見せしたいものがあります! ここで少しだけお待ちくださいっ」
何を思ったのか、彼女はそう言って立ち上がると、私の返事を聞くことなくどこかへ走っていった。
期待と不安の入り混じった心持ちで待っていると、やがて遠くから甲高い声が聞こえてきた。何やら大荷物を抱えてふらついている。私は腰を上げて、彼女の側へ駆け寄った。娘がよろめきながら差し出したのは、1着のクローク。それは、夢で見たのと同じ鮮やかな朱色をしていた。完璧なまでの一致に背筋が寒くなる。
「あの方からお預かりしたクロークです。左胸の内側をごらんになってください」
私は無我夢中でクロークを裏返した。艶やかな裏地の上で、何かが微かにきらめいたように見えた。
銀糸の刺繍。R.K――。
その1文字1文字をなぞる指先が細かく震える。口の中が急速に渇いていくのを感じる。
「まさか、ほんとうにお兄さまと同じイニシャルだったのですか?」
娘の言葉は耳に届いているのに何も返せない。彼女は、微かに震える声で続けた。
「あの日あの方は、厚地のお召し物をすっかり手放されました。そのクロークのことも、この先は要らなくなりそうだとおっしゃって……」
ああ、そうだ。彼はそう言っていた。
まるで、すべてを捨て去ろうとしているかのような、決意に満ちた声で。まばたきを忘れた私の目は、次第に焦点を失っていった。
「ずっと考えていたのですが、あの方はウィンダスを発たれたあと、どこか暖かい土地へ向かわれたのではないのでしょうか」
暖かい土地。つまり、もっと南――。サルタバルタで出会ったエルヴァーンの女の話が、脳裏をよぎった。
|
 |
|