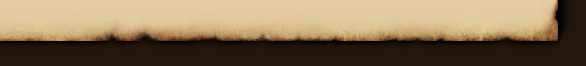|
 |
ミンダルシア大陸の南に浮かぶエルシモ島には、かつてタブナジアの民が落ち延びた港がある。サルタバルタで出会ったエルヴァーンの女が、確かにそう話していた。
仮に、件のヒュームの青年がタブナジアの出身で――、兄だったとする。
戦渦を逃れた兄が同郷の生き残りを頼って、その地を目指した可能性はあるかもしれない。だとしても、なぜ戦後10年も経ってからなのか? それまで、彼はどこにいたのか?
唸るような音と共に、強い追い風が吹いた。無数の花びらが小さな蝶のように宙に舞ったかと思うと、次の瞬間、淡い雪のように散っていった。風に踊る花びら越しに見る世界は、まるでそれ自体が夢であるかのように、おぼろげだった。
父は? ヒュームの青年が私の兄であるならば、父も一緒だったのではないか? もちろん、ふたりとも無事でいてくれたらの話だが――。
私は、娘に朱色のクロークを手渡しながら尋ねた。
「彼は、誰かと一緒だった?」
娘は、かぶりを振った。
「あの日、港に停泊していた帆船には、ほかにも人が乗っていたのだと思いますが、防具屋にお見えになったのは、あの方おひとりでした」
「すべては夢と同じ、か」
無意識のうちに、薄紅色の絨毯に覆われた桟橋の上を歩いていた私は、不思議な夢の続きを見ているような錯覚を起こした。ふと顔を上げれば、花霞のかなたに父と兄の影が蜃気楼のようにゆらめいている……。

「わたしの幼なじみが、マウラで貨物船の船長をつとめています」
目の前に回り込んできた娘が、意識を現実へと引き戻してくれた。私は、わけのわからないまま相槌を打つ。
「もしかすると彼なら頼みをきいてくれるかもしれません。いえ、きっときいてくれます!」
言葉の意味を理解した私は、娘を見つめた。彼女の眼差しは、私を捕らえて放そうとしない。真剣なのだ。
「船長の船は野菜を仕入れるために月に何度かウィンダスにやってくるのですが……。あっ、次にくるのはいつなのかしら? あの、ここで何日もお待ちになるくらいなら、いっそマウラで彼をつかまえて――」
いくら何でも、展開が急すぎる。娘の勢いに押し流されそうになっていた私は、もう一度冷静に考えようと、まぶたを閉じた。
まんまとエルシモ島にたどり着き、その地で運よく彼にめぐり会えたとしよう。もしその人物が、見知らぬ誰かだったとしたら? ……そう、私は再び絶望の淵に突き落とされることになるのだ。
「……わたしは、ずっとあの方を待ち続けていました」
何だか娘が泣いているような気がして、私は目を開けた。
「毎日胸をどきどきさせて、あの防具屋に立っていました」
彼女は力まかせに頭をねじ込むようにして、帽子を目深に被りなおした。
「だけど、待っているだけでは、なにも変わらなかったのです。そんなあたりまえのことに気づくのに、わたしは10年と2ヶ月もかかってしまいました」
静かに天を仰げば、西の雲の切れ間には夕日の片鱗が金色に輝いていた。私は、小さく吐息をもらした。
「これからマウラに向かって、その船長に会ってみるよ。君に出会ったのも、あんな夢を見たのも、きっと運命の導きなのだろうから」
「……はい!!」
娘は肩掛けかばんの底をかき回して羽根ペンとインクを取り出すと、襟元に巻いていた無地のスカーフをほどき、そこに文字を書きはじめた。
「これを船長に見せてやってください。たぶん彼は断らないと思います。あっ、貨物船の名はクビラウンビラ号です!」
それは紹介状らしかった。一生懸命書いてくれたのは嬉しいのだが、インクが生地に滲んでしまったせいで、まるで子どもの落書きのように見える。思わず私が笑うと、娘は耳の先まで真っ赤になってしまった。
「ありがとう。本当に」

スカーフを受け取った私は、彼女の案内で森の区のチョコボ厩舎へと向かった。厩務員のエルヴァーンにどう掛け合ったのか、娘はそこでいちばん足の速いチョコボを借りてきてくれた。
磨き込まれた鞍によじ上り、私は手綱を手に取った。と、その時だ。
「あのっ!」
精一杯大きな声で、娘が言った。
「やっぱり、これもお持ちになってください! そしてどうか、わたしの代わりに――」
それきり言葉を詰まらせた彼女は、両腕に抱えていた朱色のクロークを差し出した。ずっと大切にしていた青年の忘れ形見を……。
「ああ、きっと彼の元に届けるよ。約束する。それから、君!」
「はっ、はい!?」
娘は懸命に背伸びをして、チョコボの上の私を見上げた。
「どうか幸せに。ウィンダスでいちばん素敵な花嫁になってくれ」
大粒の涙をぽろぽろとこぼしながら、彼女は何度もうなずいてみせた。
|
 |
|