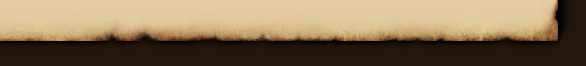|
 |
3月29日
「今日、情けをかけた敵は、明日オレの部下を殺すかもしれん。それでも生かしとけって言うのか!?えぇ? にわか神殿騎士さまよ!」
今日も捕虜の扱いをめぐって、ミュゼルワール(Mieuseloir)卿と口論になった。降伏した敵兵の命を奪うなど、たとえそれが獣人でも、女神アルタナがお赦しになるはずがない。
僕は、彼がもっとも嫌う教皇勅令を持ち出し、その場を治めた。
連戦に次ぐ連戦で、僕の所属する騎士中隊の皆が疲れ、気がたっている。
獣人集落を訪ねたあの旅は、いったいなんだったのだろう。リーダを逃がした後、自分の意志とは無関係に免罪され、神殿騎士に叙任された僕は、王立騎士団の一中隊の監察役と
して、今では毎日、獣人と人間が殺し合うのを目の当たりにしている。
中でもミュゼルワール卿率いる赤狼騎士隊の面々は、勇猛である反面、獣人の命を奪うことを楽しんでいるようにさえ見えることがある。
この戦場では、人も獣人も、ただ言葉を理解する獣にすぎないのではないか……。
僕は、自分が無力であることを、日々、思い知らされている。
女神よ、この慈悲なき戦いに、どのような意味があるのでしょうか?
3月30日
今日の戦闘は、アルタナ連合軍の勝利に終わった。
バタリア西部の稜線に沿って構築した防御柵の後方に、バストゥーク共和国の鋼鉄銃士隊が布陣。彼らの砲撃が獣人軍の主力部隊を引きつけた隙に、長躯後方に回り込んだ王立騎士隊が騎乗突撃を仕掛けたのだ。
背後をつかれ、混乱した獣人軍は総崩れとなり、気がついたときには連合軍は追撃戦に入っていた。僕は少しでも無益な殺りくを止めさせようと、王立騎士中隊の後を追って、ボ
スディン氷河へと通じるトンネルにチョコボを走らせた。
入口付近には、既に無数の獣人の屍が転がっていた。遅かったかもしれない。絶望的な気持ちになりながらチョコボを降りトンネルへと足を踏み入れた僕は、目を見張った。
なんという光景だろう。そこには、獣人ではなく連合軍の兵士の屍が累々と横たわっていた。皆、僕には正視できないような惨状だった。
息を飲んだその時、まるで壁面全体から発せられたような雄叫びがトンネルを震わせた。そして悲鳴が続く。まだ、戦いは終わっていないのだ。僕は先を急いだ。
北側に抜ける出口の手前で、ひとりの巨人と戦う騎士たちの姿が見えた。
赤い狼の紋章。ミュゼルワール卿の赤狼騎士隊だった。
最初は、彼らがただ闇雲に巨人へ群がっているようにも見えた。だけどよく見ると、騎士隊の動きには無駄がなかった。前衛は剣を振り回して巨人の気をひくだけで、決して斬り込もうとはしない。その間に後衛が射掛けた矢が、着実に彼の厚い皮膚に突き立っていく。

それでも巨人は意にも介さず、巨大な戦斧を振り回し、何人かの騎士を盾ごと吹き飛ばした。
その姿は雄々しくさえあった。今まで嫌になるくらい戦いを見てきた。でも目をそむけることができなかったのは、これが初めてだった。
命に代えてもここを守る理由があることを、その雄姿は物語っていた。
だけど、不死身とも思えた巨人にも最期の時は訪れた。左腕に刺さった矢に彼が気をとられた一瞬の隙を見逃さず、ミュゼルワール卿が跳び上がって、巨人の眉間に長剣を叩き込んだのだ。
地響きを立てて倒れた巨人を見て、騎士隊から歓声が上がる。次の瞬間、僕が恐れていたことが起きた。ひとりの従騎士が雄叫びを上げながら、倒れている巨人に斬りかかったのだ。きっと彼に戦友を殺されたのだろう。
「やめんかっ!」
僕が声を発するより早く、ミュゼルワール卿の鉄拳が彼を制した。
「彼は仲間を撤退させるため、盾となった勇者だ。その名誉を汚すこと、このミュゼルワールが許さん!」
迷いのない、凛とした声だった。
「さぁ行くぞ、野郎どもっ! まだ手柄が残ってるかもしれんぞぉっ!」
そう言って部下を奮い立たせた彼は、僕を見つけると、歩み寄って僕の肩を叩いた。
「名は知らんが、エンケラドスの右腕として連合軍を震撼させた男だ。弔ってやってくれ……」
エンケラドスの名前は、僕でも知っていた。残忍な巨人族の中でも、特に悪名高いウラノス家の兄弟のひとり。そして、その傍らに巨大な戦斧を振るう豪傑がいる、ということも。
やがて空が茜色に染まる頃、僕は宿営の側で葬儀を執り行った。それは、今日の戦闘で倒れた多くの味方のためのものだったけど、それだけではなかった。

葬儀には、王立騎士隊だけでなく、近くに宿営していた銃士隊や魔戦隊の将兵も数多く参加してくれた。味方の戦没者の名と共に、僕は巨人やその他、名も知れぬ敵兵たちのことも称え挙げた。けど、抗議の声は誰からもあがらなかった。
シヴァ座のエーオマトラに月がかかる頃、僕は初めてミュゼルワール卿と夕食を共にした。
互いに当り障りのない会話を交わしただけだったけど、それは一息つける安らかな時間だった。
そして食べ終わった時、ふと月を見上げた彼は「武人たるもの、かく散りたきものよ」と、つぶやいた。それは、あの巨人のことだった。
その言葉を聞いて、僕は気付いた。
ミュゼルワール卿が獣人に対して容赦なかったのは、彼らが獣人だからではなく、彼の敵だったからなのだ、と。
多くの血が流された今日の戦いで、彼も獣人を人として見ていたという事実だけが僕の救いとなった。
この悲惨な戦争はいつ終わるのだろう。
女神よ、すべての魂を楽園に導きたまえ。
|
 |
|