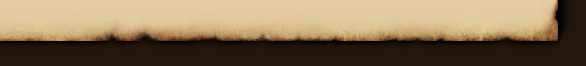|
 |
4月12日
僕たちの中隊はウィンダスの魔戦隊と共に、敗走する獣人軍を追って雲霧に包まれた峡谷を抜けた。
まさかその先の雪原に包囲陣が敷かれているとは、誰も思わなかった。辺りが晴れて気づいた時にはすでに遅く、僕たちは何百、何千というゴブリンやオーク、ギガースたちに囲まれていた。そして、彼らの頭上で全軍を指揮する有翼の影。僕たちを計略にかけたのはデーモンだった。後衛のタルタルたちに動揺が広がる。その混乱も予測していたのか、デーモンはゆっくりと右腕を振った。
それを合図に開始された獣人軍の猛攻は、盤上の駒のように統制されたもので、これまで遭遇した獣人軍とは明らかに異なっていた。絶え間なく耳に届く、味方の悲鳴。
気がつくとミュゼルワール卿が僕の前に立ち、剣を振るっていた。
「撤退命令が聞こえなかったか! 後ろの峡谷まで戻るぞ!」
包囲網を切り開きながら進むミュゼルワール卿の後について、僕は峡谷へと向かった。峡谷に近づくと、その入口に逃げ込もうとしているタルタルたちが見えた。だけど次の瞬間、僕の背後から放たれた無数の矢が彼らに降りそそぎ、何名かが転倒した。逃げるのに必死な彼らの仲間は、気づかず峡谷に入っていく。
転倒したタルタルたちに駈け寄ると、皆、急所こそ外れていていたものの、誰も立ち上がれそうになかった。
「赤狼騎士隊はここに残れ! 敵をくいとめるぞっ!!」
ミュゼルワール卿の声に応えるように、赤狼の紋章を着けた兵が彼の脇に集い抜刀する。タルタルたちをかばう僕の眼前で、赤狼騎士隊の奮闘がはじまった。
狭い地形を利用して、彼らは数えきれないオークやゴブリンと渡りあっていた。だけど、時が経つにつれて数に押され、ひとり、またひとりと力尽きていく。
そして、いつしか剣を振るうのは、ミュゼルワール卿ただひとりとなっていた。
重い一撃で獣人の姿勢を崩し、鋭いニ撃目でとどめを刺す。壮絶な気合を発して剣をさばき続ける騎士の雄姿は、あの巨人族の勇者に重なって見えた。

攻めあぐねた獣人勢とミュゼルワール卿がにらみ合ったその時、黒い影が両者の間に舞い降りた。それを見た獣人たちは、慌てたように後ずさり整列する。デーモンの将軍だった。
敵将は、剣を構え直すミュゼルワール卿を品定めするように見つめると、おもむろに背中の鞘から大剣を引き抜いた。刃からこぼれた妖しい光。満足そうに目を細めて、その切っ先をミュゼルワール卿へと向ける。
それを見た背後の獣人たちは、構えていた武器を一斉に下ろした。
「デーモンが、武人の心を解するとはな……。赤狼騎士隊隊長ミュゼルワール、参る!」
それは、1対1の死闘だった。
これほど近くでデーモン族を見たのは初めてだった。鎧とも甲殻ともつかない漆黒の体、にぶく光る瞳。そして、言葉にできない邪な何かが他の獣人とは決定的に違っていた。
両者の戦いは、どれくらい続いたのだろう。デーモンの攻撃は、まるで武器に意思があるかのように、的確にミュゼルワール卿の急所を狙ってきた。速度で勝るミュゼルワール卿は、それを紙一重でかわしていたけれど、じわじわと追い込まれていく。
彼の背が氷壁にあたった次の瞬間、甲高い音が響いた。デーモンの大剣によって、空中に弾かれるミュゼルワール卿の剣。だけど、それはミュゼルワール卿がイチかバチかの賭けに勝利した瞬間だった。勝利を確信したデーモンの手に、外した盾を打ちつけて、そのまま大剣を奪いとったのだ。
そして、その大剣によって放たれたミュゼルワール卿渾身の一撃が、敵将の右腕を斬り落とした。翼を使って、彼が大きく後方にとびのく。
「見事。……だが、ここまでだ」
デーモンは裂けた口でそう言うと、ゆっくりと左腕を振った。それを見て、再び武器を構える獣人たち。
「やはり……な。死にてぇヤツからかかってきやがれっ!」
満身創痍のミュゼルワール卿と、身動きの取れない魔戦士たち。これ以上、獣人軍に抗う術は残されていなかった。何十もの獣人たちが一斉に、たったひとりの騎士へと襲いかかる。
だけど、奇跡が起きた。突如デーモンを包むように出現した光輪が、球となってその肉体を消し去ったのだ。
続いて雪を踏みしめる音と共に駆けつけた何十もの兵士が、獣人たちに斬りかかった。援軍だった。
マントに刺繍された多頭蛇(ハイドラ)が、彼らが連合軍最強とも言われる多国籍教導部隊であることを物語っていた。
こうして、援軍の圧倒的な強さの前に獣人軍は駆逐され、僕たちはタルタルと共に救出されたのだった。
女神よ、我らを救いし御慈悲に感謝します。
4月13日
昨日の戦闘で、王立騎士中隊の7割もの兵が命を落としていた。それでも赤狼騎士隊をはじめとする彼らの活躍で、ズヴァール城攻略の要となる魔戦隊の被害は最低限にとどめられたそうだ。
負傷したタルタルを後送する適任者がいなかったため、僕は明朝、ノルバレンへ彼らを送ることになった。
午後になって、ミュゼルワール卿が僕を訪ねてきた。昨日の勲功を認められて教導部隊に編入された彼は、このままザルカバードに残るという。
「オレは赤狼の死に損いだ。これが女神の御心だというなら、せいぜい楽園の扉が開かれるまで戦い続けるとするさ……」

ミュゼルワール卿は、心中にどれほどの哀しみを抱えて、そこに立っていたのだろう。僕がかける言葉もなく黙ってしまうと、彼は取りだしたコインを僕に向けて弾いた。
「やるよ、もう不要のお守りだ」
ランペール金貨だった。それは龍王の武勲に憧れる彼を、少年時代から導いてきた宝だという。そんな大切な品を受け取るわけにはいかない。
だけど、僕が金貨を返すよりも早く彼は背中の大剣を抜き、こう静かに告げた。
「戦う牙さえあれば、あとは何も望まん」
そして、「お前だけは死ぬなよ」とだけ残して、去ってしまった。
彼は、これから死に場所を求めて戦うのだろうか。僕は、彼のために何ができるのだろうか。そして、彼と再会する日は来るのだろうか。
コインには、ランペール王の勝利宣言が刻まれている。
女神よ、いつかミュゼルワール卿に、剣を持つ必要のない安息の日々を授けたまえ。
|
 |
|