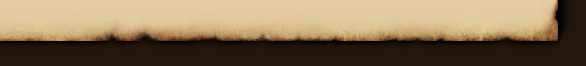|
 |
追い風をとらえたゴールデンボニート号は驚異的なスピードでパムタム海峡を渡り、エルシモ島の小さな入り江に着いた。
「ホントはアナタをここに置き去りにするつもりだったのよね。でも、ちょっと気が変わっちゃった」
てきぱきと接岸作業をこなしつつ、ヒュームの娘は意味ありげに笑った。
その数十分後、私はやけに重たい麻袋を背負わされ、ユタンガの森の獣道を黙々と歩いていた。
強い西日さえ届かない、鬱蒼とした密林。そこでは宝石のような蝶たちが舞い、極彩色の花が甘い香りを漂わせていた。
入り江を出発してから、どれくらい経った頃だったか。ある茂みの側で前を歩いていた娘が突然立ち止まり、ぐいと私の袖を引いた。木々の隙間から顔を出してみると、眼下に集落の外構らしきものが見えた。
「到着よ。あそこがカザムの入口」
私は、彼女に導かれるまま階段状の斜面を下り、丸太で造られたゲートをくぐった。そして、ゲートの側にある薄暗い岩穴を抜けた先で、ようやく麻袋を下ろすことを許された。
痺れる右腕で汗を拭い、何気なく辺りを見渡した私は、辺境の村に暮らす人々の姿に感嘆した。
高床の上に築かれた木造の家々。魚の開きを干す女は舟歌を口ずさみ、若い娘は弓の手入れをしながら人目をはばからず大あくびをしている。ある家の軒下では母と娘が寄り添うように午睡している。そこに暮らすミスラたちは、みな伸びやかで、たくましく、生き生きと輝いてみえた。
ふと、幼い少女たちのはしゃぎ声が遠くから聞こえてきた。
「にゃー! お船のおねえちゃんが帰ってきた!」
「センチョ〜、おみやげは〜?」

ミスラの少女が数人駆け寄ってきたかと思うと、あっという間に娘を取り囲んだ。
「はーい。みんな、いい子にしてた?」
娘は、その場にしゃがんで麻袋の口を開けた。彼女が次々と取り出すものを見て、私は思わず微笑した。
ジンジャークッキーに、アップルパイ、ジュースのボトルまで出てくるではないか。あの重い荷物の正体は、少女たちへの土産物だったのだ。
どれもこれも、カザムでは珍しいのだろう。その場に、わあっと歓声が上がった。その中心で、少女たちの頭や頬をなでる娘は、まるで母のように優しく笑っていた。
私は、幼くして死に別れた母の横顔をぼんやりと思い出しながら、そっとその場を離れた。
それからは、ひとりで村の中を歩き回り、幾人かのミスラに10年前のことを尋ねてみた。
「10年も昔の話だろう? 今と違って、大陸からの客人なんて滅多に見かけなかったからね。ヒュームの若い男なんかがやってきたら、それこそ村中の娘が噂したはずだよ。残念だけど、そんな記憶はないね」
水汲み場でそう聞いたのを最後に、私は手掛かり探しをあきらめ、港へと足を運んだ。
夕日はすでに沈んでいたが、西の空と海にはオレンジ色の名残があった。いつの間にか、それまで吹いていた海風は止んでいた。
明日からのことを考えようと、桟橋の端に腰を下ろしたその時、背後から聞き覚えのある声がした。
「その様子だと、ウィンダスからの預かり物とやらは、まだ手元にありそうね」
ひと仕事終えたのか、ヒュームの娘は、そのまま隣に腰を下ろした。私の旅の目的については、クビラウンビラ船長からあらかた聞かされていたのだろう。
「……ああ。受取人の手掛かりすら見つからなくてね。10年も経っているんだ。無理もないさ」

「ここじゃなければ、やっぱりノーグかしら。もしくは――」
――もしくは、兄とおぼしきヒュームの青年は、この島にたどり着いてさえいなかったのかもしれない。そんな不安が暗雲のように広がりはじめた時、すべてを見透かしているかのように娘が言った。
「ねえ。明日でよければノーグまで案内してあげてもいいわよ。どうせ地図なんて持ってないんでしょ?」
それは、思いがけない申し出だった。真意を尋ねようとした矢先、彼女は水平線を見つめてこう続けた。
「こっちもね、野暮用があるのよ」
娘は、帽子を脱いで仰向けになると、それきり、口をつぐんでしまった。
その大きな瞳に映った星たちは、どこか寂しげに揺らめいていた。
|
 |
|