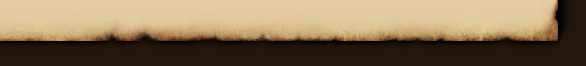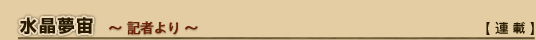 |
 |
今、私は編集部にひとり残って、この原稿を書いている。
他の編集部員は、仕事をそうそうに切り上げ、飛空艇に乗って花火見物へと行ってしまった。
噂の新型花火の取材かと思いきや、休暇をとっての単なる見物旅行というのだから困ったものだ。
だが、取材で行ったのでは心底楽しめないという彼らの主張も正しい。10マルムの彼方からでも見えるという大輪の華が彼らの心を癒し、今後の仕事への意欲につながるのであれば、それもいいだろう。
こうしている今、皆は手にした団扇で涼を得ながら、件の花火を見上げているのだろうか。あるいは、集って「金剛稲穂」などの小さな花火を楽しんでいるのかもしれない。
一口に花火といっても、その来歴はさまざまだ。東方から輸入された花火や、ゴブリン製の花火。王立騎士が夜戦に用いていた軍用品までも、今では民間に出回っているという。
それゆえ、一昔前まで各国の人々にとって、「花火」は、自分たちの国で用いられているものだけを指す言葉だったらしい。
しかし現在では、なにかの催しがあれば、そこで多種多様な花火を目にすることができるようになり、人々の認識は大きく変わった。
その一因は、やはり冒険者だ。
新しいものをためらうことなく試し、また楽しむ術を心得ている冒険者によって、花火の需要が増大した結果、商人やモーグリは世界中から花火をかき集めてくるようになったからだ。
しかも、彼らは花火を楽しむだけでは飽き足らず、自らの手で合成する術を習得するに到り、その普及は世界的規模に増大したのである。
皆が休暇を取ってまで見物に行った新型の打ち上げ花火にしても、冒険者の需要と供給が遠因であることは間違いない。
本紙が創刊した頃、花火を知る者はまだ少なく、冒険者たちもヴァナ・ディールにとって小さな存在だった。
それが27号を数える今日では、普及する花火の種類も増え、冒険者たちもヴァナ・ディールに不可欠な存在へと成長した。
そして、これからも花火は普及し続け、冒険者たちも更に必要とされることだろう。
ヴァナ・ディール トリビューンも、そのような冒険者たちに追いつくため、花火のように、多様性を模索する時期に来ているのかもしれない。
|
 |
|